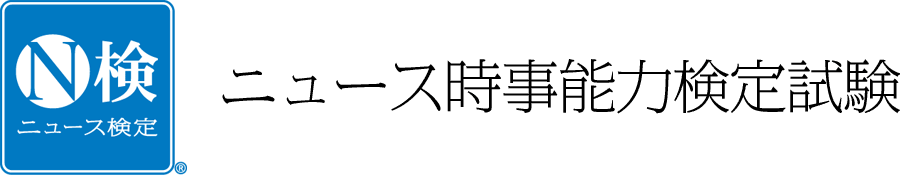社会人・一般
現在、会社員として働いています。小学生のころから、新聞やテレビなどのニュースに触れることに興味を持っており、それがきっかけで、社会を学べる大学に通い、勉強をすることにつながりました。しかしそれまではこの検定の存在は知りませんでした。
ある日書店にて検定案内のポスターを偶然見かけ、「これはチャンスだ」と思い、まずは準2級から受験し、就活のとき、履歴書に書きアピールしました。
あれから数年、もっと時事力をつけたく、2級に挑戦しました。2級の問題は、テキスト・問題集が基本なので、テキストは全ページを何度も読み、問題集も、2級の部分はもちろん、それと併用する形で準2級も解きました。準2級の問題の応用でもあり、似たような問題が出ると考えられるため、参考も兼ねて私なりの勉強方法です。また、未掲載の内容、最新のニュースは、日々の報道で確認し、わかりやすくまとめました。
試験当日は「合格したい」という重圧がのしかかるもテキストの内容は満点とる気持ちでのぞみました。応用問題もありましたが、予備知識等も活用し、最後までやり遂げました。
1か月後、合格証と成績表を手にしたときはうれしかったです。次は1級受検、合格という目標を達成したいと思います。合格点の高さは把握しているので、2級の成績表の分析とニュースの深堀りを通し、さらに時事力を磨いていこうと思います。
私は山口県の日本語学校で教員をしています。主にアジア諸国からの留学生に日本語を教える仕事です。また在日外国人メンバーによる国際合唱団の運営にも携わり、歌を通じての地域の多文化共生の推進も目指しています。さらにウェブライターとして福岡県北九州市のグルメやイベント、人物を紹介する記事も書いています。
こうした地域社会に関わる多様な活動をする中で、現代社会が直面している時事ニュースの理解は自分にとって不可欠な前提となると考えるようになりました。私はかつて大学や大学院でドイツ文学・哲学を学んだ者ですが、一方で政治、経済、環境と言った分野については十分に研鑽を積んで来なかったことに負い目を感じていました。そこでこの「ニュース時事能力検定」を見つけ、そのような分野も含め貴重な学び直しの機会になるのではと考えました。
学習法としては公式テキストと問題集を購入し、特に太字のキーワードを意識しながら要点を押さえ、チェックを重ねました。うろ覚えだった用語は特にネットのニュース等も調べて意味確認を行いました。項目の中ではやはり外国人労働者に関わる制度や難民受け入れの問題が自分の職業との関係もあり特に興味を惹きました。
時事ニュースというものはもちろんアップデートされ続けるものなので、来年度以降もこの検定の機会を活用して行きたいと考えています。
私は、就職活動で内定したニュース番組制作を中心に行うテレビ番組制作会社の薦めでニュース検定1級・2級に挑戦することになりました。
新社会人のスタートをきるにあたり、ニュースを正しく読む知識と自信を得ることができたことが大きな収穫と感じています。
受検に向けては、まずテキストに目を通してから問題を解き、間違えた部分を改めて確認することを繰り返していました。また、不正解の問題は問題文のコピーを取ってノートに張り付け、自分で解説を書き込んでいました。次にその知識を問われた際に間違えないよう、意味などを頭に浸み込ませることを意識して取り組みました。
受検本番では、ニュースに出てくる用語とその意味を覚えることだけでなく、用語同士の関係や時系列の変化を理解していないと答えられない問題が多いと感じました。受検後、1級の合格ラインに届いているか不安はありましたが、合格通知を見たときはとても嬉しかったです。
受検を通して、ニュースや新聞などの専門的な用語に対しての苦手意識が薄れたと感じます。学習の中で用語の意味をしっかり理解できたことに加え、勉強の過程で用語とその意味を結び付ける習慣が身につきました。以前はカタカナやアルファベットのニュース用語に特に苦手意識を持っていましたが、受検後は頭に入りやすくなったと思います。
また現在、新社会人として日々仕事に取り組むうえで、ニュース検定の合格は自身の大きな自信になっていると感じます。新人として働いていると、時に失敗することや、自分の努力の方向が正しいのか迷うこともあります。そんな中で、ニュース検定合格という目に見える形で成果を得られたことは、仕事する上での心の支えの一つになっています。
私は、能開センターという進学塾の中学受験部門で社会科主任を務めております。日々、生徒たちが志望校に合格できるようにさまざまな校舎で社会科の授業をしております。
ニュース検定を受検するようになった契機は、2020年から数年間続いたコロナ禍の頃、自分自身の社会科に関する知識を補強し、授業内容に幅を持たせ「社会科は単なる暗記科目ではなく、『今』の世の中を深く理解するうえで欠かせない科目であること」を生徒たちに強く伝え、興味をもってもらい社会科の学力をさらにあげてほしいと思ったことでした。また、勉強系の某有名ユーチューバーの動画に強く感銘を受け、生徒たちとともに自分自身も勉強して今以上に知識を増強させたいと思ったことも受検の契機となりました。
そこで、まず歴史系(日本史)の資格試験の勉強を始めて、その資格試験の1級に複数回合格することができました。さらに現代社会の検定試験にも挑戦してみたくなり、そのような試験がないかどうかネットで検索したところ、ニュース検定があることを知りました。
早速、ニュース検定の公式のテキスト・問題集を購入し学習したところ、社会科を教えている身でありながら、まだまだ知らないことがあることに気がつきました。ニュース検定2級はすぐに合格することができましたが、1級はレベルがとても高く、2回ほど不合格となりました。1級は合格率がとても低く、合格率10%未満のときもあると知り、1級合格に向けての自分の勉強法が正しいのかどうかを再検討することにしました。
そこで不合格となった問題を徹底的に分析した結果、1級に合格するためには、「いかに多くの知識事項」を知っているかという「知識量」より、「いかに時事的な出来事の原因やその背景を理解できているかどうか」が重要であることに気づきました。
そこで、知識事項を「覚える勉強」から、時事的な出来事の原因や背景を「理解する」ことに重点をおいた勉強にシフトしました。具体的には、約30分程度の通勤時間(往復)や仕事の休憩時間(約1時間)の隙間時間、寝る前の30分間に、ニュース検定の公式テキストを5回以上、徹底的に読み込みました。
この時に注意したのは「覚えよう」とせずに「理解しよう」と意識しながら読み込んだことです。このような勉強をしているうちに、私自身の勤めている能開センターでの社会科の授業内容や授業方法に変化が出てきて、単に知識事項を生徒たちに覚えさせるような指導ではなく、その原因・背景に重点をおいた授業になっていき、とても役立ちました。生徒たちの反応も以前よりも良くなり、数ヶ月後になっても1度教えたことを覚えてくれる生徒が多くなったような気がします。また、私自身が勉強していると、生徒たちの気持ちがリアルにわかるようになり、より生徒たちの勉強に対する悩みなどが理解できて、机上の空論ではない現実的なアドバイスができるようになりました。
さて、そのような勉強の日々も過ぎ去り、いよいよ試験前日になりました。試験前日(土曜日)は、朝から夕方まで市内にある図書館にずっとこもって、ニュース検定の公式テキストを再度、全テーマを読みこみ、さらにニュース検定の公式テキストには掲載されていない最新のニュースも、ネットなどを使って学習しました。
試験当日の午前中は仕事があったので会社に出社し、その後に大阪の長堀駅の近くにある試験会場に急いで向かいました。生徒たちにいつも「最後まで諦めてはいけないぞ!」とよく言っているので、私自身も試験会場に向かう電車の中で論述問題対策の内容など再チェックし、試験会場に到着しても、ニュース検定の公式テキストを読みこみました。
試験終了後、少し手応えはあったものの、8割は厳しいような気がしました。1週間後の解答速報を見て自宅で自己採点すると78点でした。合格ラインが8割程度なので、あと1問ぐらいの差での不合格と予想しました。ただ、合格ラインの8割程度の「程度」という言葉に少しの希望をいだいていました。
そして発表日当日、ネットで調べると、「合格」の2文字が画面に出ました。思わず声を出してしまいました。何歳になっても「合格」というのは嬉しいものだと思いました。それと同時に、勉強は「やり方」がとても重要であることを実感しました。受検に向けての学習において本当にいろいろと勉強になったとともに、今後もさらにさまざまな資格の勉強を続けていこうと思います。もちろん、ニュース検定の試験も、何度も受検し続けようと思っています。
勉強というと、いわゆる高校受験や大学受験などで終わってしまいがちですが、「年齢を重ねるごとに学力・理解力が向上するのだ!」と信じて、生徒たちとともに私自身も頑張っていこうと思います。そして、「今の自分が一番、学力が高いのだ」という自信を持って、生徒たちに社会科を全力で指導できるように邁進いたします。
最後に、この合格体験記を読んでくれている能開センターの生徒の皆さんや1級合格をめざしている皆さまへ…。一緒にどんどん勉強してレベルアップしていきましょう。そして、受験(受検)が終わっても、さまざまなことを学び続ける人になっていきましょう。私自身もまだまだ新しいことに挑戦していきます。ニュース検定の試験会場などで私を見かけたら、ぜひ声をかけて下さい。
業務でのスキルアップのために受験しました。
私はWebニュース編集の仕事をしています。具体的にはマスコミ各社から送られてくる記事の中からユーザーにとって影響の大きいものや興味関心の高そうな記事を選び、配信する仕事です。たくさんある記事の中からどれが配信に値する記事なのかを見極めるスキルが必要となってきます。
エンタメなどはある程度見極めのハードルは低いですが、時事となると人によっては苦手意識がある人もいます。
かく言う私もその一人で、仕事を始めた当時は国内の時事はもちろん、海外の時事もちんぷんかんぷんという状況でした。この状況を打開すべく、ニュース検定の受験を決意しました。
いざテキストを読み始めると最初は7割くらい理解できませんでした。「これはまずい!」と思い、途中挫折しそうにもなりましたが、結局テキストを5周、問題集を5周こなしました。その他、憲法や経済など関連書籍の読み込み、1カ月の新聞をまとめた雑誌の購読などで対策していきました。
1級の初回受験時は「やはり難しい」と感じました。単に知識をインプットするだけでなく、関連付けて覚えることが必要だと思います。
初回受験はあまり手応えがなく、落ちたと思っていましたが何とか合格していました。その後は学習のルーティンも確立でき、続けて2回3回と合格することができました。
1級を取得してからは時事も自信を持って見極めることができ、同僚にも積極的にアドバイスを送っています。国内政治など世の中の解像度が格段に良くなったと思います。どのような業種の方でも取得に向け学習することで自分の人生に役立てることができると思います。
1級取得で自信がついたので、今後は様々な取得にチャレンジしていきたいと思います。
私は、専門学校時代にニュース検定に合格しましたが、久しぶりに『ニュース検定を15年ぶりに受験』をしました。その当時は、テレビやインターネットでニュースは観ていて時事は好きだったものの、政治に関心がありませんでした。ここ2,3年でコロナになり、とある『政治家の動画や与野党のネット党首討論などを観るようになり、関心がでてきたこと』と、専門学校時代の卒業アルバムを見て、その当時は、受かるのに自信がなくて、下の級を受けましたが、同級生が、私より一つ上の級に挑戦していて合格していたのを思い出し、今度は、『私もその級を取得するぞ』と思うことができました。後日ニュース検定の公式テキスト&問題集を書店で買って、繰り返し勉強して、テレビ(ニュースや国会中継や政治家が出演している討論番組等)や政治家の所属している党のネット配信(生配信も含む)を観ると、憲法改正や首長などかなり参考になりました。
今年の6月に受けましたが、残念ながら地元では、検定は実施していなかったため、隣県で受験しましたが、以前よりも、手ごたえはあったと思います。また、専門学校時代に比べて、『討論番組や政治家のネット動画やニュース番組を観るようになったり、統一地方選挙や衆議院選や参議院選の投票もする』ようになりました。受験や就職だけでなく、「話の話題にも役立つのではないか」と個人的にそう思います。ニュース検定の申込から本格的にはじめて、試験日前日まで問題集を繰り返してひたすら問いたり、政治家が出演している報道番組やネット動画など見て、試験に挑んだ結果、合格した時の達成感や15年前の自分には、越えられなかった壁を一つ越えられた様な気がします。
毎日新聞社や朝日新聞社、全国の地方新聞社が主催する「ニュース時事能力検定試験」は、2020年に創設14年目を迎える。昨年11月に実施された第47回検定では累計志願者が45万人を突破。中学・高校・大学生を中心に、社会人へも支持が広がっている。毎日新聞社が発行する月刊「ニュースがわかる」に「オジさんの話を聞いて!」を連載中の時事芸人、プチ鹿島さんもそのひとり。新聞の読み方や社会情勢の見方の解説が分かりやすいと好評だ。その鹿島さん、昨年11月のニュース検定に挑戦し、見事1級と2級に合格した。11月の1級合格率はなんと4%ほど。超難関突破はいかにして果たされたのか。「仕事の合間を見つけて勉強した」という極意や新聞、メディアへの関わり方を語ってもらった。【聞き手・毎日教育総合研究所社長、澤圭一郎】
澤 1、2級一発合格おめでとうございます。
プチ鹿島さん ありがとうございます。いやあ、でもかなり難しかったですよ。
澤 今回の1級は問題も難しかったようで、全国で9人しか合格しませんでした。仕事されながらですからすごいことです!
鹿島 まさか1級も合格するとは思わなかったのでうれしいです。記述式問題よりも択一問題がとても難しかったです。
澤 どのように準備されたのですか。
鹿島 テレビやイベントの仕事の合間をぬって、テキストと問題集を勉強しました。ともに3回はやりました。ほんと、検定までの1カ月は人生で一番勉強したと思います。まさに受験生と同じ心情で。寝る前の1、2時間は毎日テキスト読んで問題集を解いてましたね。最初にテキストを読んでから問題集を解く。次は問題集を解いてみて、ひっかかった問題をテキストで復習する。何度もつまずく問題、つまり苦手な分野が浮き彫りになってきます。そこで、ゲーム感覚で「さあ、どうやって攻略してやろうか」なんて作戦を考えてね。テキストに赤い字で書かれている点は大事な部分ですし、自らラインマーカーで印をつけながら勉強しました。
澤 鹿島さんならではの作戦、勉強法もあったとか。
鹿島 テキスト、問題集に書かれている出来事を記事検索したんです。いまはパソコンで検索が容易ですね。「パリ協定」とか「RCEP」なんて単語も出てくるじゃないですか。それを覚えるというより、記事を検索して内容を読み直したんです。すると「ああ、そういうことだったのか」と深く理解できる。知ってはいたけど、出来事の流れを再度たどることで「本当に理解できた」と思います。楽しみながら勉強できたんですね。私にとってストレスにならない勉強の仕方でした。
澤 時事芸人ならでは、ですね。
鹿島 ニュースは日々動いていますから、テキスト・問題集を勉強して基本は身に付け、さらに毎日のニュースも追いかける。それが効果的だったのだろうと思います。
澤 好きな分野、得意なテーマはありますか。

鹿島 政治分野は好きだし得意なんです。10代のころから政局に関心があって。
澤 それはまた珍しいですね。
鹿島 父が買ってくる週刊誌や月刊誌を読むのが好きでした。そこには、政治家の人となりや人間関係が書かれている。田中角栄元首相の派閥の話やそこから独立していく竹下登元首相の思いなどが描かれている。「政治家といっても人間なんだなあ」と。どろくさい面があるんですね。それが面白かった。
澤 そこが今の仕事につながる原点でもあるんですね。
鹿島 そうです。お笑いの世界に入って、最初はコンビを組んでいたんです。でも、時事的なネタは扱わなかった。私個人の「趣味」にとどめておきました。相方もいるしね。コンビを解散して30代後半でピン芸人になった時「自らが面白いと思っている時事ネタで勝負していこう」と決めた。原点は、子供のころから親しんでいた雑誌や新聞なんです。
澤 最近は紙の新聞を読む方が減ってきています。
鹿島 私は紙が好きですね。私はいま、13紙に目を通していますが、特にスポーツ新聞は必ず紙を読みます。カラフル感や見出しの面白さ、レイアウトの楽しみは紙の編集でないと味わえない。ですから、一般紙も紙そのものでなくてもパソコンやスマートフォンで「紙面ビューアー」(紙の新聞を電子化したもの)を見ます。
澤 新聞を味わうんですね。
鹿島 味わい方があります。毎日新聞、朝日新聞、読売新聞といった一般紙に社説がありますよね。
澤 あります。私、書いていました。
鹿島 堅いイメージがありますよね。偉そうというか。
澤 すみません(笑い)。
鹿島 でね、私は社説を擬人化して見ているんです。「師匠」と呼んでます。社説は大所高所から論じるので。たまに、論じていないこともありますが。

澤 ははは。
鹿島 例えば、成人の日の社説は「師匠がまた若者に説教しているな」などと見ながら読むわけです。説教の仕方が師匠によって違うのです。つまり、新聞社によって視点や論点に違いがある。
澤 確かに違いますね。
鹿島 だから、同じテーマで読み比べると面白いんです。読売の師匠はこんな調子だが、毎日の師匠は別のことを話している、なんてね。「看過できない」というフレーズが好きで多用する社説があることを発見したりして。突っ込みを入れながら読んでいるとなかなか楽しいんですよ。なので、各紙の1面トップ記事、コラム、社説は読み比べして楽しんでいます。新聞自体も擬人化して、各紙を性格分けして見ています。朝日さんは、産経さんは、などとね。舞台で時事コントするときのネタにもなるのです。
澤 多くの方がそんな読み方をしてくださると良いのですが。
鹿島 あとね、新聞の記事はプロの記者がしっかりと裏付けをとって書いているから信用できるのです。調べて書いているから。だからプロ。私たちはそんな時間は作りにくいから、お任せしているわけです。私たちは楽して確かな情報がとれる新聞をもっと利用すればいい。そこがインターネット上にある情報との違いではないでしょうか。さらに、どこか笑える「おかしみ」が必要なのではないかと感じるんです。いま、ネットの世界を中心に、他者に対して厳しいですね。攻撃的だったり罵倒したりする。そうではなくて、偉そうな社説も「師匠」と呼んで、ちょっとおかしみを交ぜて見る。私はそんな味わい方が好きなんです。さらに紙の新聞の良さを言いたいのですが「関心がない出来事も見出しが目に飛び込んでくる」。これ、重要です。ネットの世界だと、関心のない出来事は調べないし情報を取ろうとも思わない。でも、新聞紙面は「一覧性」があるから、関心のないことも目に入る。それが大事。「あれ、どこかで見たな」と意識の中に残るのです。
澤 ぜひとも多くの方に今の話を伝えてください。特に若い人に(笑い)。
鹿島 いま、時代の大きな転換点ですよ。その時代に生きていることを、若い人は味わってほしいです。20年後、「令和って元号になった時はさあ」なんて、後輩たちに話して聞かせられるんですから。教科書に載る出来事があった時代に生きているんです、いまの若い人は。体験者なんですね。だから、目いっぱい、時代や社会を味わってほしい。吸収してほしい。新聞も使って。
澤 ニュース検定から新聞の活用法まで、幅広いお話ありがとうございました。1級合格者に話していただくと重みが違いますね。
鹿島 テキストと問題集は毎年更新されるので、これからは生涯学習として毎年買って勉強しますよ。ホント、よくできているし、ためになる。私は今後「N検1級合格者」って目で周囲から見られるわけで、気を抜くわけにはいきませんからね。でもね、テキスト持っていない人は、これは手に入れたほうがいいですよ、間違いなく。必ず役に立ちます!