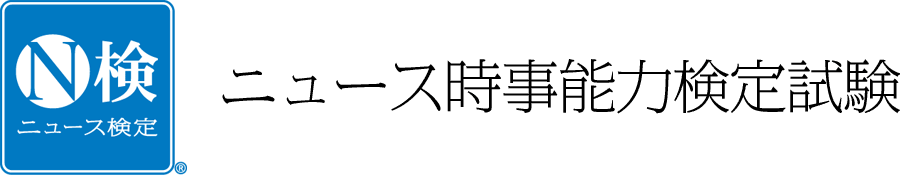企業・団体 活用事例
ブルーネットワーク合同会社は報道・ニュース番組の制作会社です。
2020年度より内定者研修としてニュース検定を導入され、入社後も自己啓発支援として受検を推奨されています。
代表の米澤様にニュース検定導入のきっかけや、導入後の変化などを伺いました。
きっかけはコロナ禍での新卒研修
以前から検定の存在は知っていましたが、コロナ禍に入社早々自宅待機になってしまった新卒社員が自宅でできる研修はないか、と考えたときにニュース検定に思い至りました。公式テキストを自宅に送り、勉強してもらうことにしました。目標がある方がよいかと思い、検定合格を目指して勉強するよう勧めてみました。

導入前後の変化、よかったこと
当社はテレビニュースを軸とした番組制作を行っているので、前提としてニュースの基礎理解がある方がスムーズに社会人スタートができます。そのため、検定導入前は、内定者に対して「日々ニュースを観ること、分からないことは調べること」と促していましたが、個人により対応に差がありました。
導入後は、公式テキストをもとにした幅広い分野を学習することで、知識が偏ることなく、ニュースの基礎知識が習得できるようになりました。
また、「検定受検」という具体的な目標があることで、自主学習にも意識高く取り組めています。会社としても結果通知から内定者の得意な分野や苦手な分野を把握することができるのは利点だと感じています。
内定者観点としても、ニュースの基礎理解はもちろんのこと、学びや検定受検を通して、また「合格」という成果の可視化により、自信をもった状態で入社に至れるようになったとの声を聞いています。
ニュース検定が仕事で役に立ったと感じる場面

当社の場合はニュースの基礎知識があるかないかで仕事のやりやすさや成果に大きな差がでます。例えば、さまざまな分野のニュースについて取材、街頭インタビューなどを行うときにも、ニュース理解の土台があることで、取材対象者への質問や話の展開に広がりが出ます。入社後は、ニュースを知っている前提で話が進んでいきます。ひとつひとつのニュースの背景や基礎知識が説明されることはありません。基礎知識が習得できていれば、実務で本来覚えていくことに専念できますので、必然的に成長スピードも加速します。
若手社員からの声
・これまでニュースを理解して見ているつもりだったが、詳しくない分野も多くあったことがわかり、ニュース全体の知識をつけることができたと感じた。特に理系の自分にとっては政治分野の知識に不安があったが、選挙のしくみや政府の構造のような基盤となる知識を改めて学んだことで自信を持って入社することができた。ニュースを見るための入り口になるような試験だと感じた。

・就職前の準備としてとても良い機会でした。公式テキストがわかりやすく、苦手な分野を学び直すこともできました。5分野を意識して見ることができ、単体ではなく複数のニュースを関連付けながら見られるようになりました。
・入社後すぐに政治に関する街頭収録に参加しましたが、テキストの知識が役に立ちました。基礎知識を知っているかいないかで仕事のやりやすさが大きくかわるので内定期間にニュース検定を受検しておいて良かったです。
採用活動を通じて、社会人になる皆さんへ
学生時代は人生においてかけがえのない時間です。やりたいことはとにかく何でもチャレンジして、たくさんの経験を積み、悔いのない充実した学生生活を送ってください。学びでも、サークルでも、アルバイトでもあらゆる経験が自分の財産になると思います。
協会からのコメント
検定料・公式教材は会社が負担し、1級合格者には奨励金を出すなど、会社として内定者・社員のみなさまの時事力強化に取り組まれていると感じました。
2024年度の検定では初めて1級合格者が出たそうです。合格体験記はこちら
最近では応募時点ですでにニュース検定を取得している方も増えており、2級以上を取得している方には書類選考免除の優遇措置をとられています。
社員が社会に対する関心を失わないようにするにはどうすればよいか。さらに仕事にも役立つ知識や考え方を身につけさせるには何をすればよいのか――。コンサルティング会社「エフアンドエム」(大阪府)は、ニュース時事能力検定試験を社員教育の一環として積極的に活用し、社会や世界の動向に関心を向けさせることに成功している。その活用法や社員の実感、人事部門の見方を聞いた。
「以前は別の企業向け試験を導入していたんです。でも、それは資格試験ではなかったこともあり、試験対策としてのテキストが無く、その分勉強する範囲が広いため何を頼りに勉強を積み上げればよいか社員は戸惑っていたようです。そのため、もともと世の中や経済に対する興味関心が強い人が良い点数を取っていた。それでは『教育』にならないんです」。同社の森中一郎社長はそう説明する。エフアンドエムは、全社員にニュース検定2級の取得を義務づけている。3年の間に3級、準2級、2級と段階を踏んで合格させる設計だ。6年前から社員教育に取り入れており、上々の効果を生み出している。
「ニュース時事能力検定の良い点は、勉強範囲が明確なテキストがあること。これで基礎をおさらいし、検定に挑む。合格すればモチベーションが確実に上がります」。

ニュース時事能力検定を仕事に生かしているエフアンドエムの社員。「社会への関心を高めるツールとして最適です」と笑顔で話してくれた。
さらに同社は、自社で開発したeラーニングの仕組みで、社員のスマートフォンに毎日1問、ニュース検定の問題を配信。通勤時間などを使って1~2分で回答できるため、こつこつと積み重ねる習慣も身につくという。
入社3年目の足立昴也さん(24)は「テキストでの勉強とともにスマホで検定への意識付けができるのでとても有り難い」と話す。検定合格はもとより、仕事に直結することがやりがいにつながるという。「生命保険会社への営業を担当していますが、お客様同士の話にしっかり入っていくことができます」。どういうことか。「仕事以前の雑談です。もちろんスポーツや砕けた話もありますが、米中の貿易摩擦や国内政治など、間接的に仕事に関する雑談をされていることがあります。そこに入って、自らの考えを述べる。『こいつは時事的な話もできる』と認めてもらえるんです」。取引先の営業マンの知識や力量を、そんな雑談で見ているのだ。「ニュースや時事問題なんて学生時代には関心がなかった。自分の生活には関係がないとも思っていましたが、仕事をするようになると断然『武器』になる」。
同じく入社3年目の左藤唯さん(24)は、為替相場の動向や日銀の金融緩和政策の見方といった「今の社会情勢」について話す営業先の責任者の思考を理解できるようになったという。「黙っていては相手にも伝わらない。自らの知識や考え方を話すことで、より自分を理解してもらえ、営業機会を作り出すことにつながっていると実感しています」。
一方、入社2年目の石井大さん(23)は営業先でのプレゼンテーションに役立っていると話す。「時事的な知識があることでプレゼン内容も深まり、勉強会に参加いただいている皆さんに認めてもらえて仲良くもなれる」。営業先に一目置かれる存在になることで、仕事に対するモチベーションが大きく高まるのだ。
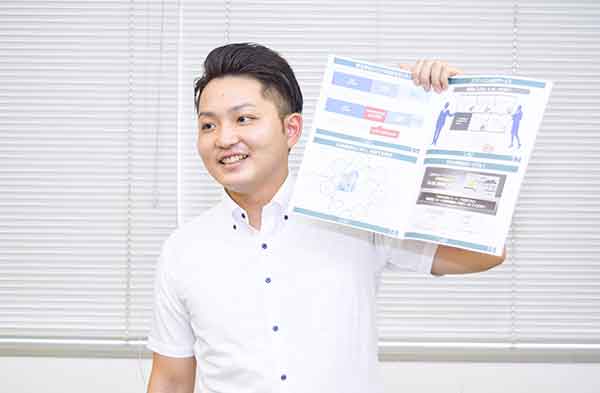
人事担当者はどう見ているのか。人事経営企画部の松尾麻希部長は「学ぶ姿勢を癖づけることができている」と感じている。「検定に合格することを義務付けること、その一助として毎日問題を配信し勉強することを半ば『強制』することで、こつこつ学ぶことを生活の中に定着させる。今の若い人にはそうしたほうが良い、効果があると見ています」。
しかも、自社の社員の品質を保証できるともいう。「担当する仕事の知識があるのは当然。さらに社会に対する関心がある、ということが会社全体の信用を高めていると思います」。
仕事に上乗せされる形で、検定を受けることに社員の不満はないのか。「確かに忙しい時は『大変だなあ』とは感じます。でも、それを超えて、仕事に結びつくことを思えば苦にはならないです」。

検定試験前には、営業部で集まり過去問題に取り組むなど対策もするという。スマホへの配信など、若い社員が取り組みやすく工夫をしている点も大きいが、森中社長は「時事問題などの教養は新人のころから鍛えるべきで、社員の話にもあったように仕事に直接役立つことをもっと認識したほうが良いと思います。検定も合格すればより意欲も高まります。ニュース検定はこれからも活用していくつもりです」。